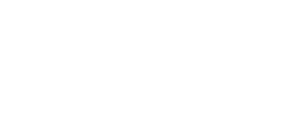事業創造と産業振興を通じて
新しいライフスタイルを提案します
仙台フィンランド健康福祉センターは、仙台とフィンランドのビジネスを促進する非営利プロジェクトとして、仙台市とフィンランド共和国の産業振興協定(2005年〜)に基づき設立されました。
仙台・宮城の健康福祉産業の発展を目指すとともに、本市産業の国際化を推進するための拠点として、Well-being(=「健康福祉」のほか「よく・生きる」)という言葉が含む、生活の質(QOL)の向上に資する様々な分野において、新製品・サービスの開発や海外展開のサポートを行っております。
健康福祉機器・サービス開発支援
健康増進、介護予防、介護福祉等、主にシニアの生活の質の向上に資する機器・サービスの開発をサポートするほか、IT事業者の介護業界への新事業展開(Care Tech)を推進するため、IT事業者と介護事業者の連携を促進しています。
仙台市とフィンランド共和国の産業振興協定に基づき、2005年より両国企業の海外展開をサポートしてまいりました。フィンランド共和国からEU市場へ、また、ASEAN地域へのゲートウェイとしてタイ王国にもサポート範囲を広げております。初めての海外ビジネスでもスムーズに始められるように現地での幅広いネットワークを活かして、準備から立ち上げまでをサポートいたします。
設置運営:公益財団法人仙台市産業振興事業団
〒981-0962
宮城県仙台市青葉区水の森3-24-1
TEL / 022-303-2666
FAX / 022-303-2667
〒980-6107
宮城県仙台市青葉区中央1-3-1アエル7F
TEL / 022-724-1212
FAX / 022-715-8205